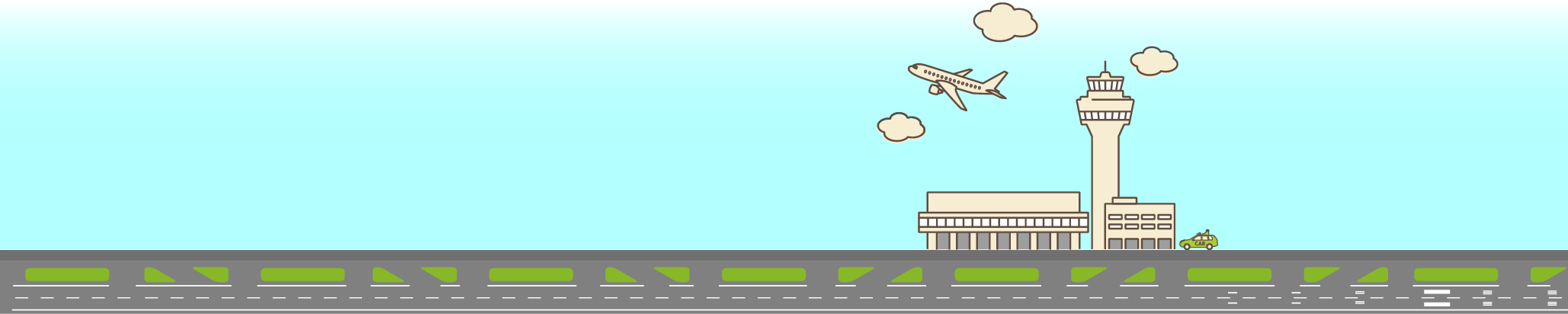
受験案内は、採用試験の募集期間にあわせて人事院・国家公務員採用試験情報NAVI-国家公務員採用試験 受験案内一覧にて配布します。
航空保安大学校パンフレットについては、こちらから電子データをダウンロードいただくか、資料請求フォームから印刷製本版を請求いただくことができます。
受験料は無料で、受験申込に必要な書類もありません。在籍している(若しくはしていた)学校等から提出する書類もありません。
受験申込の際は、
①人事院・国家公務員採用試験インターネット申込みにアクセスし、
②「事前登録」の後、
③「航空管制官採用試験」若しくは「航空保安大学校学生採用試験」への申込
を行ってください。
※②「事前登録」まででは、受験申込手続を完了したことにはなりませんので、必ず③「受験申込」まで行ってください。
日本国籍を有しない者は受験できません。
人物試験(面接試験)における具体的な質問例はお答えしかねますが、当校では、真に航空保安職員になりたいと考えている方、協調性のある方、他者とのコミュニケーションを図れる方を求めており、人物試験を通じて確認させていただきます。
なお、航空分野に詳しいか、詳しくないかによる有利不利はありません。
採用人数は毎年一定とは限りません。
各年度の採用予定数は、人事院が採用試験情報の一つとして官報に公告しており、受験案内にも掲載されます。
最新の情報は人事院・国家公務員採用試験情報NAVI-採用情報-専門職試験(大卒程度・高卒程度)ににてご確認ください。
|
2024年度試験 |
2023年度試験 |
2022年度試験 |
|||||||
| 1次試験受験者数 | 最終合格者数 | 採用予定者数 | 1次試験受験者数 | 最終合格者数 | 採用者数 | 1次試験受験者数 | 最終合格者数 | 採用者数 | |
| 航空管制官 | 472 | 135 | 130 | 418 | 94 | 83 | 428 | 85 | 72 |
| 航空保安大学校 | |||||||||
| 航空情報科 | 164 | 42 | 21 | 140 | 44 | 20 | 193 | 42 | 20 |
| 航空電子科 | 137 | 61 | 30 | 111 | 76 | 30 | 123 | 78 | 30 |
※最終合格者となっても、実際には採用に至らない場合もあります。
最終合格者は、全員が採用候補者名簿に記載されます。
一方、採用者は、採用予定数(定員)を上限として採用候補者名簿の上位から順に意志を確認して内定を行うため、合格者数と採用者数は異なります。
なお、採用内定者からの辞退などにより採用予定数に空きが出た場合は、次点の合格者に意思を確認し、新たに採用の内定を行います。
最初は座学で基本的な知識を身に付けてもらい、その後、実技の授業を行います。実技は、現場で実際に使用する機材を模した本格的な実習装置を用いて、一人ずつ又はグループ単位で指導します。
なお、令和7年度における実技の授業時間は、航空交通管制職員基礎研修が約36%、航空情報科2年が約33%、航空電子科2年が約19%です。
受験した科ごとに異なる採用試験を実施して採用しておりますので、入学後に科を変更することはできません。
教官(日本全国の航空官署に配属されていた航空管制官、航空管制運航情報官、航空管制技術官など)及び特任教官(外部の大学教授等)が授業を行います。
食費、水道光熱費などの生活費のほか、業務に必要な以下の国家資格の申請費用等が必要となります。
・航空無線通信士(航空管制科、航空情報科)
・陸上無線技術士(航空電子科)
※試験手数料などの詳細は、こちらをご覧ください。
なお、授業料や教科書代、住居費はかかりません。
学生寮は、校舎に隣接された鉄筋コンクリート造りの14階建ての建物で、研修生・学生は、研修に専念いただくため、原則として学生寮(家賃無料)に入っていただくこととなります。
各部屋は、バス・トイレ付きの個室となっており、室内には机・椅子・ベッドのほか、エアコンなども備えられています。また、共有の洗濯機や寮生同士が交流するためのコミュニケーションスペースも設けられています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
平日の昼食は、お弁当を注文することができますが、その他の食事については、各自で用意していただくことになります。
そのほか、自炊をする場合には、学生寮の各フロアに1か所ずつある給湯室で行うことができますし、近隣にあるコンビニやスーパーマーケット、レストランを利用することもできます。
はい、自由に過ごして問題ありません。勉強する人、スポーツをする人、外出する人など様々で、クラブ活動も活発に行われています。
ただし、当校の研修生・学生は国家公務員であり、原則として兼業は禁止されていますので、アルバイトはできません。
航空管制官採用試験または航空保安大学校学生採用試験に合格して採用されると、国家公務員になりますので、本校での研修期間中も給与が支給されます。
航空保安大学校在学中の給与月額(地域手当含む。)は、航空管制科の場合で約242,000円、航空情報科及び航空電子科の場合で約207,000円です。このほか、期末手当・勤勉手当(いわゆるボーナス)なども支給されます。
当校の研修は、平日の8時30分から17時15分までカリキュラムがぎっしりと詰まっているため長期休暇を設けていませんが、お盆時期(4月に採用された航空交通管制職員基礎研修生は7月)に3日間の休暇を設けています。
本校の研修課程を修了(一般の学校における卒業)すると、日本全国の航空官署に配属され、所定の研修等を受けた後、航空管制官・航空管制運航情報官・航空管制技術官等に任命されます。なお、本校の研修生・学生は、国家公務員として採用されていますので、研修課程修了後に就職活動をする必要はありません。
航空保安大学校のカリキュラムは、国土交通省職員を養成する専門コースとなっていますので、本校を修了しても学位取得はできません。
航空保安大学校は、通常の大学と違い、航空の安全を守るための職員を養成する施設です。このため、成績不良等により職責を果たせないと判断される場合、退学処分となり国家公務員としての身分を失うことがあります。
勤務する航空官署は日本全国にあり、職種によって異なる官署に配属されることとなります。具体的にはこちらをご覧ください。
航空保安職員は、日本全国に張り巡らされた航空交通ネットワークの安全を支えているため、すべての航空官署が円滑に航空保安業務を遂行できるよう、転勤(人事異動)に応じていただく必要があります。
配属先は個人の希望のみで決まるものではありませんので、出身地の近くでずっと働きたいといった願いは、まず叶いません。また、航空官署は北海道から沖縄まであり、転勤によって大きく環境が変わることもありますので、環境変化への適応力も求められます。
しかし、様々な勤務地での経験は自身の成長に繋がりますし、多くの仲間と出会えることは人生の大きな糧となるでしょう。また、勤務先としては空港や航空交通管制部以外にも、国土交通省本省や東京・大阪の各地方航空局、航空保安大学校等の教育機関など様々な活躍の場があり、国際機関への派遣など世界各国の方と仕事をする可能性もあります。
一部の空港や航空交通管制部では、24時間切れ目なく業務を行っていますので、深夜を含む夜間の勤務に就くことになります。また、ほぼすべての空港が365日稼働していますので、土日祝日やお盆、年末年始なども勤務があります。
ただし、勤務時間は一日7時間45分、休日は4週間で8日が基本となりますので、平日が休みになるメリットもあります。
仕事、昇進、待遇なども含め、ありません。
令和7年4月1日時点の女子の割合は以下のとおりです。
・航空交通管制職員基礎研修 44.2%
・航空情報科 58.5%
・航空電子科 35.6%
本校では、学校教育機関・自治体など対象となる方以外の施設見学は受け付けておりませんが、10月に開催される空の日・オープンキャンパスで一般公開を行っています。
オープンキャンパスの具体的な開催日及び内容については、「オープンキャンパス」ページでお知らせしておりますので御覧ください。
※施設見学については「視察・見学」ページを御覧ください。
まず、ツバサノシゴトを御覧いただき、その後、国土交通省ホームページ内の各ページを見ていただくことをお勧めします。
こちらは、過去に開催したオープンキャンパスに際して『航空保安大学校の学生/研修生に聞いてみたいこと』を募集し、皆様から応募いただいたご質問と学生/研修生の回答をまとめたものです。
航空保安大学校の学生/研修生に聞いてみた!(2024年7月版)
航空保安大学校の学生/研修生に聞いてみた!(2025年3月版)
航空保安大学校の学生/研修生に聞いてみた!(2025年10月版)